若手・女性社員×ミドル層社員
×社外監査役 座談会 第2部
「イキイキと安心して
成長できる働き方」を考える
[第2部]未来の企業価値を高めていくために
「すべての社員がイキイキと安心して成長できる会社」とは、どんなものか——。第1部で見えてきた課題をふまえ、参加者たちは未来に向けた対話に臨みました。キーワードは、「人財とスキル」「組織文化・社風」「共通の価値観」。一人ひとりの気づきや想いが交錯する中で、新たな可能性へと向かうヒントが、少しずつ見えてきました。
❶ 人財とスキル
─ 岸 : まずは「人財とスキル」について考えてみましょう。皆さんの話からも、学ぶことへの意欲や、スキルアップのあり方に対するさまざまな思いが見えてきました。
─ K. Y : 私はキャリア入社でこの分野に飛び込んで、わからないことだらけでしたが、だからこそ新しい知識を得るのが面白いです。
─ C. H. : 私もキャリア入社ですが、現場を見に行った時、研修で学んだことが実務でどう活かされているのかが一気にわかり、とても印象に残りました。土木・建築業界が初めての場合は、現場のリアルを体験できる機会がとても大事だと思います。
─ M. O. : 教育の必要性は強く感じます。私は先輩という立場なので、後輩の指導に十分な時間を使いたいのですが、ほかの自分の仕事との両立が難しいこともあります。限られた時間の中で、教える側にもサポートが必要だと思いますね。
─ 岸 : 第一線を退いたベテラン社員の方が新人研修で教壇に立つという試みが、一部の部署では始まっているそうですね。それにより、現役社員は「教える」という業務から解放され、ベテラン社員の経験を共有できる良い機会になりますね。
─ Y. H. : そうですね。学びや育成のあり方は、現場での実感とどう結びつくかが大切です。制度としての研修だけでなく、日々の実務の中で学びが深まるような仕組みを整えていきたいと考えています。
─ 岸 : 社員は、企業にとって価値を創り出してくれる重要な存在です。サポートして育てる環境は、ぜひ個人の意欲や経験に寄り添うものであってほしいと願います。
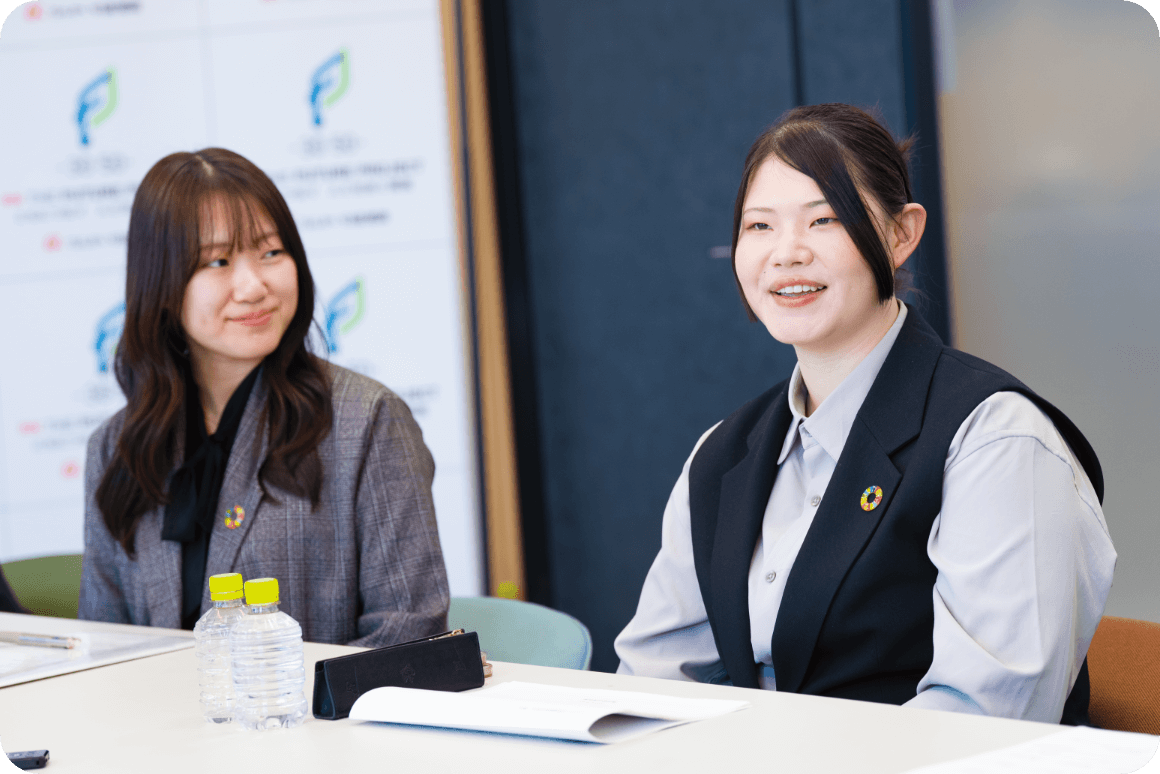
❷ 組織文化と社風
─ 岸 : 次に「組織文化や社風」について考えてみましょう。研修や業務の中でも、部署や立場を越えた“つながり方”や“コミュニケーション”に課題を感じている人は多いのではないでしょうか。
─ D. O. : 組織文化というのとは少し違うかもしれませんが、世代間の交流、たとえば新人との関係づくりは、やはり大切だと感じています。経験の差があるぶん、どう伝えるかを工夫して、良好な関係を築いていければと思っています。
─ 岸 : T. K.さんは、参加者の中で一番の若手ですね。世代差のようなものを感じたことはありますか?
─ T. K. : 世代差というより“部門差”を感じますね。私は建築部門ですが、研修では土木部門の方が実践的な内容だった印象があります。測量やCAD※など、現場につながる内容が組み込まれていて、うらやましく思うことがありました。建築の研修も、もう少し現場視点が強くなるとうれしいです。
─ C. H. : 私も建築部門ですが、研修で他部署の方に教えていただいたことがあって、すごく勉強になったことがあります。
─ 岸 : その時は、“部門差”や“部門の壁”がなくなった…と感じられましたか?
─ C. H. : そうですね。もっと自然に部門を越えた連携が多くなればいいのに、と思いました。
─ E. H. : 組織は、どうしても縦割りの要素が残りがちですよね。特に建築と土木のように部門がはっきり分かれていると、研修や業務の方針も別々になり、普段の業務ではほとんど接点がありません。だからこそ、こうした場をきっかけに、部門をまたいだ交流が活発化するといいですね。
─ 岸 : そうですね。いわゆる組織の“壁”は多くの企業にも見られるものですが、誰かが壊してくれるのを待つだけではなく、一人ひとりが少しずつ低くしたり、壁を溶かしていくための意識や行動が大切だと思います。
※CAD:Computer Aided Designの略。コンピュータを用いてデジタルで設計や製図を行うツールのこと

❸ 共通の価値観
─ 岸 : 最後に、「共通の価値観」について考えてみましょう。多様な働き方や生き方が尊重される現代では、企業は自社が“何を大切にするか”をすり合わせていくことが求められます。S. A.さんは、仕事と育児の両立を大切にする、という選択をされているようですね。
─ S. A. : はい。でも、限られた時間で実現するのは大変です。例えば、育児のための時短・時差制度を活用して子どもの送り迎えをしていますが、そのぶんの給与は変わらないような手当や制度があれば…と思うことはあります。
─ E. H. : 若手や女性が活躍できるには、そうした多様な働き方を支える制度が“価値観の土台”として必要だと思います。それを整えるのは、私たち世代の責任です。
─ Y. H. : そうですね。しかし、制度を導入するには課題も多いです。たとえば現場でフレックスタイム制を取り入れた場合、監督が少し遅れて現場に入るだけでも、その時間、協力会社の作業が始められなくなることがあります。全体の作業工程に影響が出る。それを防ぐには、業務の見える化や引き継ぎの仕組みを整える必要があります。そのためにも、DXの活用が欠かせないと感じています。
─ 新井 : 現場にいるT. K.さんはどう思いますか? フレックスは可能でしょうか。
─ T. K. : 管理責任者なら、朝礼をリモートにするなどの工夫で実現できると思います。ただ、私たち若手が担う実務では、まだ難しさを感じます。でも、例えば早朝業務を交代制にするなど、何かしらの方法があるかもしれません。
─ 岸 : 立場や役割によって、働き方の実現方法も変わるということですね。「共通の価値観」は、違いをなくすのではなく、違いを認め合いながら支え合う中で育つもの。そのための対話と工夫を積み重ねていくことが、企業文化を創り、未来の企業価値を高めていくのだと、改めて感じました。


